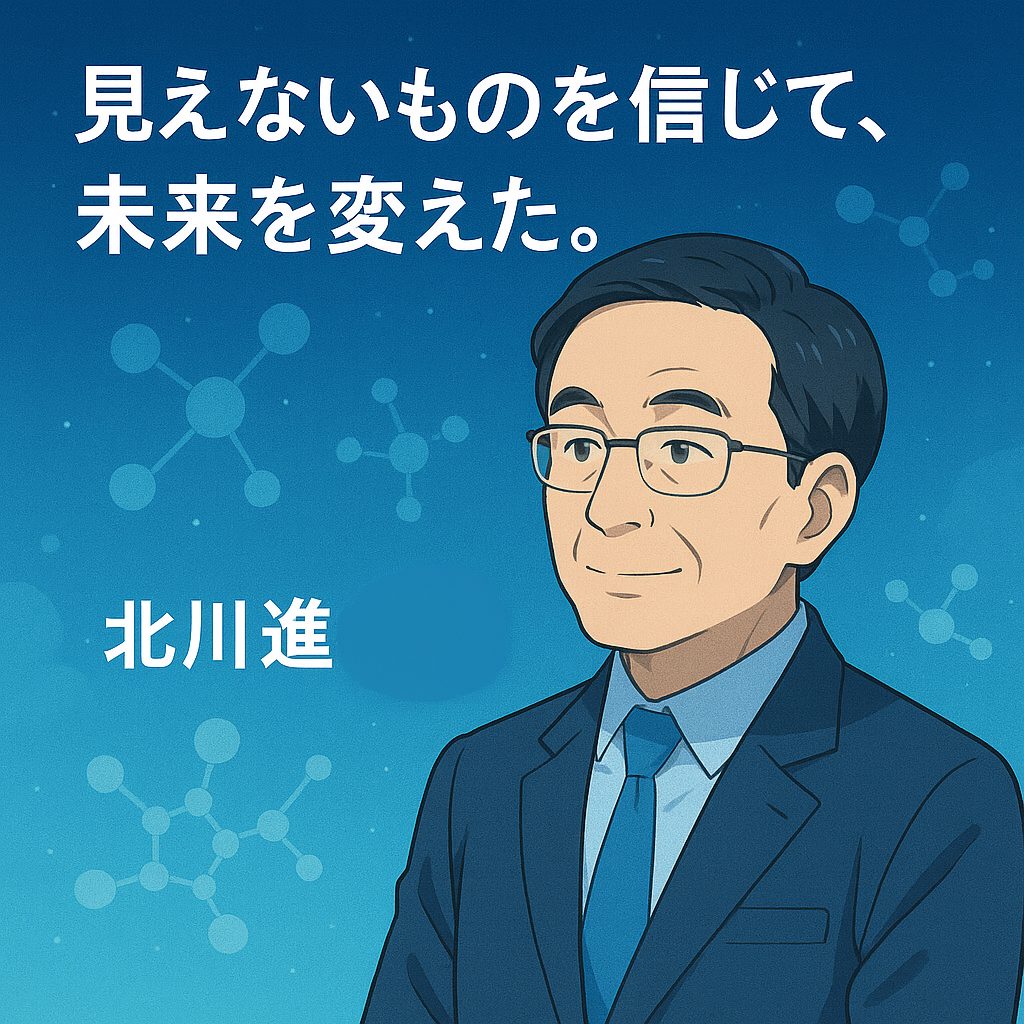「空気の中に“部屋”をつくる──そんな夢みたいな科学を、本気で形にした人がいる。」
何もない“空気の中”に、見えない部屋を作れるとしたら?
その小さな部屋には、ガスやにおい、エネルギーまでも閉じ込められる。
そんな不思議な空間を、現実にしてしまった科学者がいます。
その名は**北川進(きたがわ・すすむ)**さん。
京都大学の名誉教授であり、世界が認める化学者です。
彼が研究したのは「見えない空間の中の世界」。
分子の動きを操り、目には見えない“空間”をデザインするという、
まるで空気に建築をするような発想でした。
今回は、北川さんの著書『配位空間の化学 最新技術と応用』を手がかりに、
彼が見ていた“目に見えない世界”の面白さをやさしく覗いていきます。
- 北川進氏は、目に見えない「空間」を操る化学者。
- 「空気の中に部屋を作る」ような発想で世界を変えた。
- 著書『配位空間の化学』を通して、その発想をたどる。
- 本記事は、専門知識よりも“発想の面白さ”に焦点を当てる。
北川進という人
「見えない世界を“見えるようにした”科学者。──分子の中に未来を見た。」
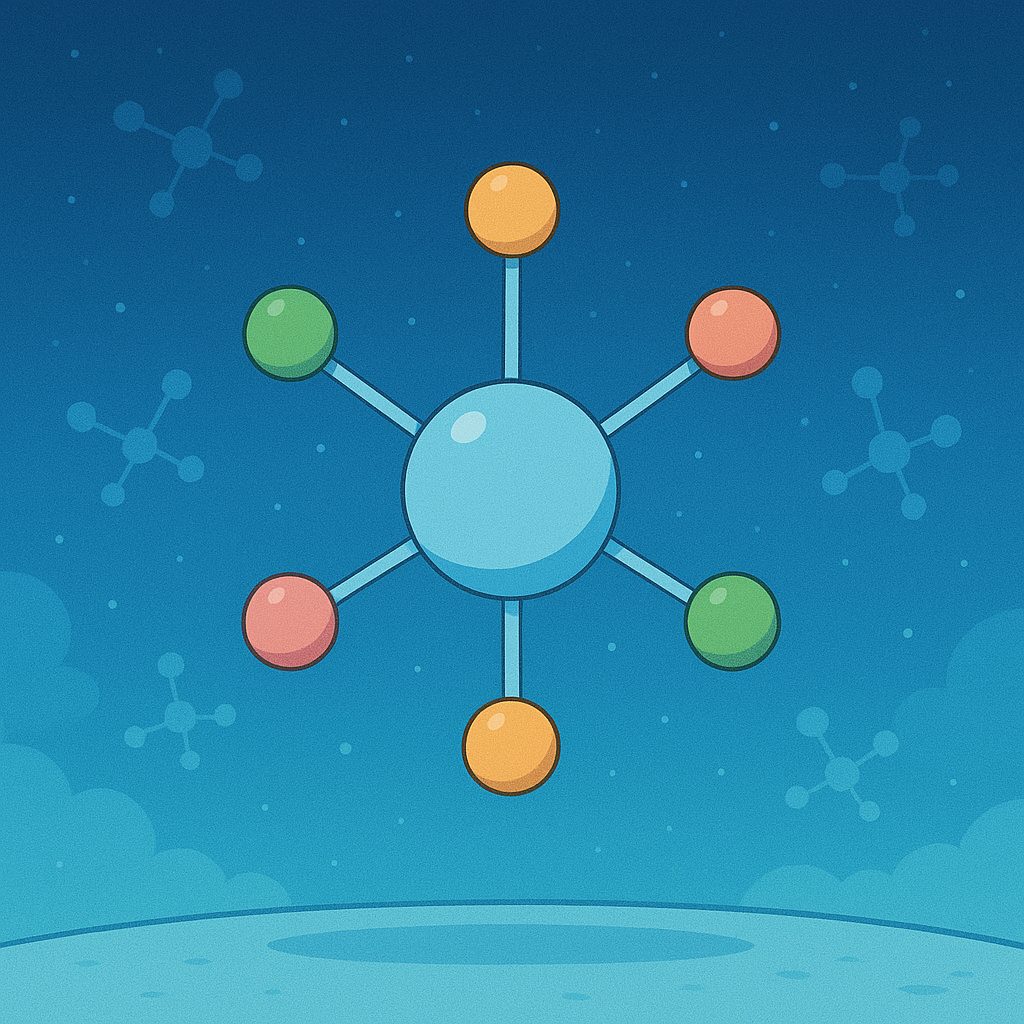
京都大学名誉教授、そしてノーベル化学賞受賞者の北川進さん。
世界中の研究者が“MOFの父”と呼ぶほど、その功績は大きなものです。
彼が追い求めたのは、「分子のすき間に潜む、もうひとつの世界」。
普通の人には見えないミクロの空間を、自在に設計しようとしました。
その研究の中心にあったのが、
「多孔性配位高分子(MOF:Metal-Organic Framework)」。
これは、金属と有機分子を組み合わせて作る“分子レベルの骨組み”。
まるで分子のレゴブロックのように、穴(空間)を自由に設計できるのです。
北川さんの発想は、とてもシンプルです。
「空気の中にも、まだ使われていない“空間”がある。
ならば、その空間を“使える形”にすれば、世界はもっと変わる。」
こうした考えから生まれたMOFは、
・ガスの吸着や貯蔵
・においの除去
・医薬品やエネルギーの新しい輸送手段
など、未来の産業を支える“見えない素材”として注目されています。
北川さんのすごさは、「世界のルール」を変えたこと。
化学の世界では、空間は“空っぽの場所”だと思われていました。
けれど彼は、「空間こそ、可能性の宝庫だ」と証明したのです。
まるで、何もないと思われていた場所から未来を掘り当てた探検家のように。
- 北川進氏は、京都大学名誉教授でノーベル化学賞受賞者。
- 研究テーマは「見えない空間=配位空間」の設計。
- MOF(多孔性配位高分子)を発明し、分子レベルで“空間”を操る技術を確立。
- 空間を「何もない場所」ではなく、「新しい価値の源」として示した。
配位空間ってなに?
「分子の中にアパートを建てた──それが北川進の“配位空間”だ。」
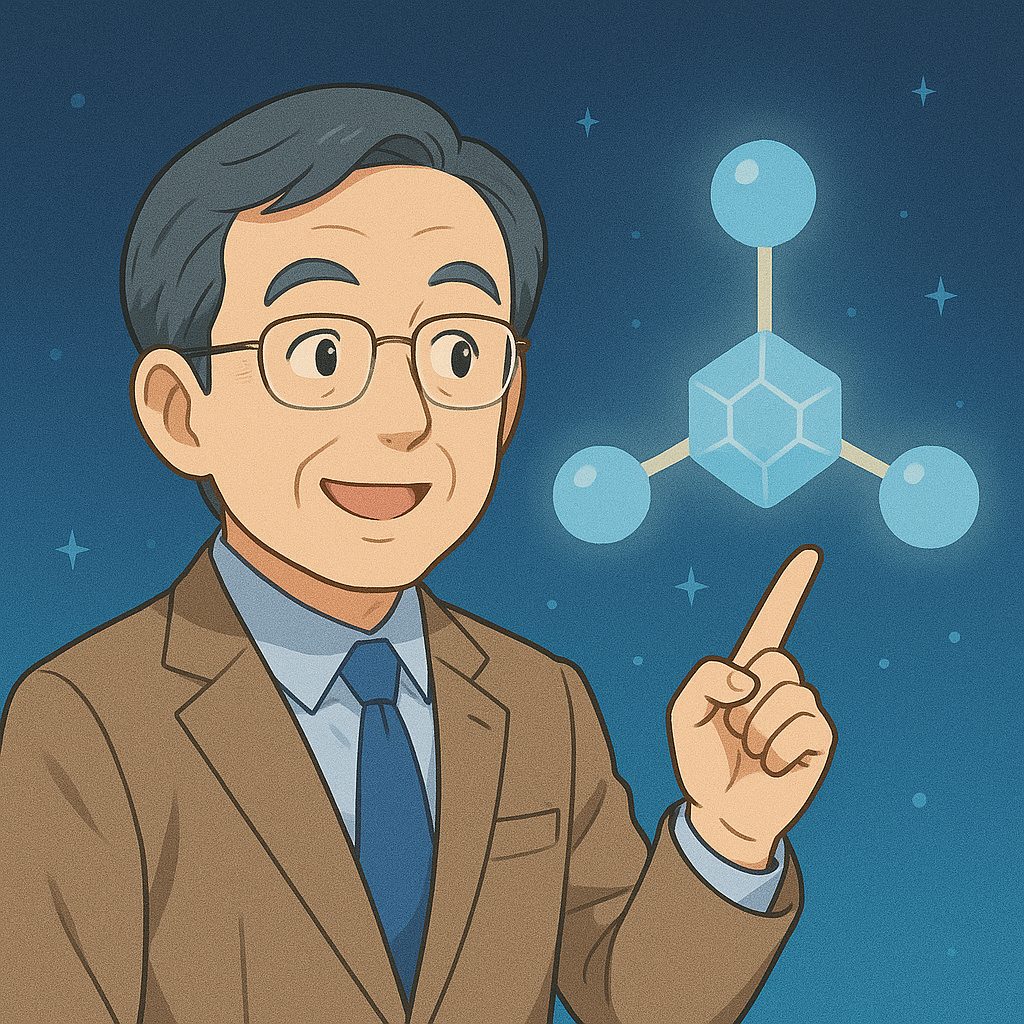
「配位空間(はいいくうかん)」という言葉。
ちょっと難しく聞こえますが、想像してみてください。
もし、分子たちが住む“アパート”があったらどうでしょう?
そこでは、小さな分子たちが部屋に入ったり、通路を通って出たりしています。
北川進さんは、その**“分子のアパート”を設計する建築家**だったのです。
普通の物質は、分子同士がびっしり詰まっていて“空間”がありません。
でも北川さんの作った素材は、
分子と分子のあいだに無数の「すき間」=空間があります。
そのすき間は、たとえば──
- ガスを閉じ込めて貯める“倉庫”になったり
- においの分子をキャッチして消臭したり
- エネルギーを運ぶ“通り道”になったり
まさに**見えないけれど役に立つ“小宇宙”**です。
北川さんは、この空間を「デザインする」という考え方を広めました。
それまでの化学は、「物質を作る」ことが中心。
でも北川さんは、「物質の中の空間こそ、操るべきもの」と考えたのです。
言い換えれば──
分子の中に、“世界のルールを書き換える余白”を見つけた。
この発想は、今では「MOF」や「配位高分子」という新しい研究分野として広がり、
世界中でエネルギーや医療、環境の未来を変える技術につながっています。
科学を「物を作る技術」から「空間を使う発想」へ。
北川さんの研究は、まさに化学を建築に変えた革命といえるでしょう。
- 「配位空間」とは、分子の中にある“すき間”を自在にデザインする考え方。
- 北川氏は、分子を建材のように組み立てる「分子の建築家」。
- その空間は、ガスやにおい、エネルギーなどを“閉じ込める”ことができる。
- 化学を「形」ではなく「空間」で考える──それが配位空間の発想。
『配位空間の化学』という本
「分子を並べ、空間を描く──それは、科学であり、アートでもある。」

『配位空間の化学 最新技術と応用』は、
北川進さんが監修した、研究の集大成ともいえる一冊です。
タイトルだけを見ると、専門的でとっつきにくい印象を受けますが、
実際に読んでみると、そこには“科学の向こう側”が見えてきます。
この本は、分子の世界をただ説明するだけではなく、
**「見えない世界を、どうやって人の手で形にするか」**を追いかけた記録です。
たとえば、
- どんな素材が、どんな構造を作るのか
- どのように分子たちを並べれば、空間が生まれるのか
- その空間を使って、何ができるのか
そうした研究の積み重ねが、この一冊に詰まっています。
でも面白いのは、読み進めるうちに、
“科学書”というよりも**“創造の物語”**のように感じられること。
北川さんの研究には、どこか芸術家の視点があります。
分子をただの「材料」として扱うのではなく、
「配置」や「光の入り方」までデザインしているのです。
まるで、
「見えない世界に、美しい建築を建てる建築家」。
そんな表現がぴったりです。
『配位空間の化学』は、
専門家だけでなく、創作やデザインの分野に関心のある人にも
“発想の自由さ”を感じさせてくれる一冊です。
科学の本を読むとき、
「正解を知る」よりも、「問いを持つ」ことが大切だと気づかされます。
北川さんの文章には、そんな**“考える余白”**がちゃんと残されているのです。
- 『配位空間の化学』は、研究成果だけでなく“発想の記録”でもある。
- 北川氏は分子を“材料”ではなく“デザインの一部”として捉えている。
- 科学を通じて「見えないものを形にする」創造の姿勢が感じられる。
- この本は、専門家以外にも“発想のヒント”を与えてくれる。
北川進という人
北川進さんの発想から学べること
「見えないものを信じる力が、未来をつくる。」
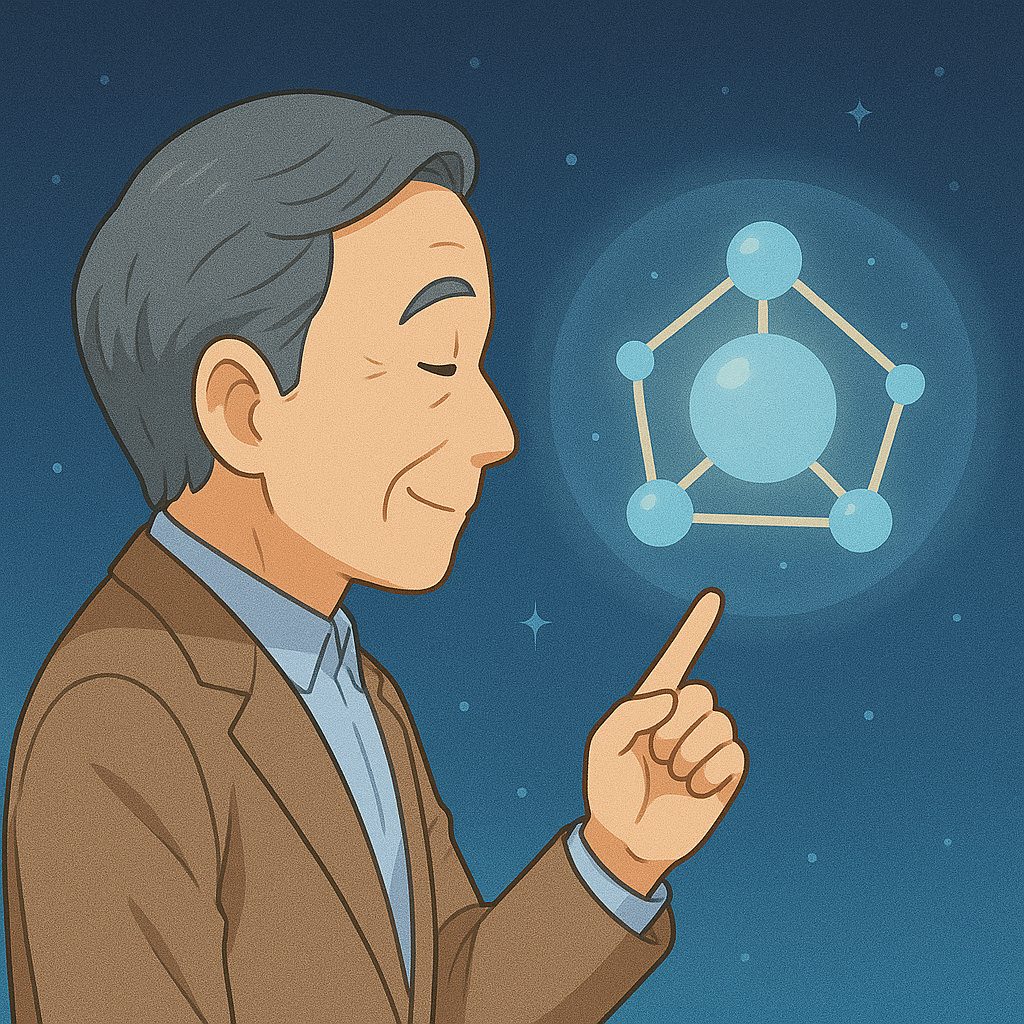
北川進さんの研究を読んでいると、
それは単なる科学ではなく、“考える姿勢そのもの”のように感じます。
彼はいつも、目に見えないものを相手にしてきました。
空間、分子、エネルギー──どれも手で触れることはできません。
でも、**「見えないからこそ、工夫の余地がある」**と考えたのです。
たとえば、実験がうまくいかないとき。
多くの人が「ダメだった」とあきらめてしまう場面でも、
北川さんは「これは、新しい発見の入口だ」と言います。
失敗を“終わり”ではなく、“次の扉”に変えてしまう。
この考え方こそ、北川さんの研究を支えてきた原動力でした。
もうひとつ印象的なのは、楽しむ姿勢です。
北川さんは、学生たちにこう語ったそうです。
「研究はね、“遊び心”がないとつまらないよ。」
科学というと、真面目で難しいものと思われがちですが、
彼の中では“ひらめき”や“想像”が、研究のいちばんのエンジンでした。
それは、分子の世界を舞台にした探検のようなもの。
どんなに小さな発見でも、そこには「やってみよう!」というワクワクがある。
そして北川さんは、どんな研究にも**「人間らしさ」**を忘れませんでした。
科学は人の手で作られる。だからこそ、
思いやりや感性、ひらめきが大切だと語っています。
この姿勢は、どんな仕事や生き方にも通じるものです。
目に見えない努力を積み重ね、見えない未来を信じる。
その先に、誰も見たことのない“発見”が待っているのです。
- 北川氏の研究姿勢は、「見えないものを信じる力」。
- 失敗を“終わり”ではなく“発見の入口”として受け止める。
- 科学には「遊び心」や「ひらめき」が欠かせない。
- 研究にも人生にも、“楽しむ気持ち”が未来をつくる。
- 北川氏の言葉は、学問を超えて“生き方のヒント”になる。
まとめ
「何もないと思っていた空間に、“未来”は隠れていた。」
空気の中に、目には見えない“部屋”をつくる──
そんな発想から、北川進さんの研究は始まりました。
分子のすき間を操り、空間そのものをデザインする。
その考え方は、化学の常識を変えただけでなく、
「見えない世界にも無限の可能性がある」という希望を教えてくれます。
私たちの毎日も、見えないものに支えられています。
努力も、信頼も、思いやりも、目では見えません。
けれど確かに存在し、世界を少しずつ変えていきます。
北川さんの研究は、そんな“見えない力”を信じることの大切さを思い出させてくれます。
科学の本なのに、読み終えたあと、心の奥にあたたかい光が残る。
もしあなたが、
「世界はもう出尽くした」と感じるときがあったら、
思い出してください。
見えないところにこそ、新しい発見が眠っている。
そして、その小さな発見が、やがて未来を変えるのです。
- 北川氏の研究は、「空間そのものをデザインする」発想から生まれた。
- 「見えないものを信じる」姿勢が、科学と人生を動かす原動力。
- 分子の世界を探求することは、人間の想像力を広げる行為でもある。
- 『配位空間の化学』は、学問を超えて“世界を見る目”を変えてくれる本。